1789年7月17日
気のせいでも、思い込みでもなく、確かに光が見えた。
この薄暗い部屋では、俺の目には人のシルエットすら判別できないはずなのに、オスカルが飛び込んで来た時、ほんの一瞬だったが、眩い光が俺のもとに舞い降りたのを、俺ははっきりと見た。あるいは、それは肉眼で見た映像ではなく、俺の魂がオスカルの魂をとらえたのかも知れない。
言い尽くせないほどの後悔と詫びの言葉。体力の限界を越えた身体への気遣い。隠していた病。戦闘と混沌を生き抜いてくれたことへの感謝。何にもまして変わりようのない愛おしさ。再会の喜び。想いは幾晩語り明かしても伝えきれない。なのに、おまえが俺の名を呼び、俺のもとに走り寄っってその身を俺の枕元に投げ出した時。
俺の首に廻されたおまえの腕に自分の腕を重ね、柔らかな絹糸の束に手を差し入れ、おまえの鼻先を俺の頬に引き寄せた時。暖かい涙で濡れた熱い頬を合わせ、弾む息遣いの愛しさに胸がはち切れそうになった時。
「本当によく…やった…な…」
口に出せたのはたった一言だった。オスカルは、声になるかならないかの小さな吐息で応えた。俺を抱きしめる彼女の力強さ、微かな振るえが充分過ぎるほど想いの全てを語っていた。
交じり合う互いの体温と脈動が、大切なものを取り戻した喜びを静かに謳う。いつしか、ふたりの中を流れる血潮は一つになって二人の体を駆け巡る。それだけで、俺たちは世界を手に入れた者よりも満ち足りていた。
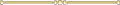
私はどこにいたのだろう。私が私をぼんやりと他人事のように眺めていたような気がする。市庁舎にに通じるサン・トノレ街道は2層の分厚い人垣で延々と埋め尽くされていた。新旧取り混ぜたタイプのマスケット銃が槍のように人垣から突き出ている。果たしてまともな銃弾がこめられているのだろうか。おそらく正規の銃弾など手に入らないだろう。
銃先に銃剣はついていたりいなかったりまちまちだ。槍に鎌、果ては棒切れに荒縄で刃物をくりつけただけの、即席武器も人垣から所狭しと突き出ている。民兵と野次馬の区別もつかないカオスな群衆は『国王万歳!』繰り返し叫んでいる。しかし、その歓声の中には少なからず敵意の混じった『国民万歳!』の怒号も混じっていた。
自分が自分でないような浮遊感の中でも、私は私のすべきことは明瞭に理解していた。思考力も判断力も普通に働いていた。俄か作りの民兵を統括するために、一定の距離で部下を配置する。定期的に状況報告をさせ、非常事態の段階ごとにいく通りかの指示を出す。部下達はよく動いてくれて、熱狂に我を失うことなく、秩序を保つ任務を全うしていた。
国王陛下を乗せた8頭立て馬車が、地味な装飾に鞍替えした軽騎兵に、守られると言うよりは監視されるように取り囲まれて目の前を通り過ぎる。馬車窓を通して口元を真一文字に結んで目を閉じていらっしゃる陛下の横顔がちらと見えた。
それなのに何の感慨も涌かない自分に驚く。その自分をさらに無感動に眺める自分もいる。幾層にも自分自身が分かれて漂っているようだ。地面から巻き上がる埃が目に辛かった。
行列の後からは100名程だろうか、国民議会議員が続き、その後を従僕が大勢続く。鳴り響く太鼓とラッパに大波のような歓声、人いきれ。身体が沸騰するように熱くなったり寒くなったりする。眩暈と頭痛。目を開けているのも辛くなる。せめて喀血だけは起きないで欲しい、とぼんやり思う。身体は辛いのに、それもまるで他人事のように見ている私がいる。
馬車と行列は遠ざかって行った。国王陛下がパリ市庁舎に到着したのちに何が起きるのだろう。群集は一向にその場を離れようとはしなかった。街中が機能を止めて事態を見守っている。
「隊長!」
誰かが叫んだ。ぐらり、と身体が傾いて急に地面が近くなった。地面にたたきつけられる、と思う間もなく太い腕がわたしを抱き留め、わたしの視界を遮った。気づけばその腕に体重をあずけたわたしの一部が悲鳴を上げた。違う!この腕ではない!何が違うのかもわからないまま、心のどこかが悲鳴をあげ続けている。遠い遠い声。
負傷して休んでいるはずの部下が知らせを届けてくれたのはその時だった。彼の意識が戻った!
幾重にもぶれていたわたしが一人になった。感覚が蘇った。目に映る情景が急に色彩を取り戻し、この世には色というものがあったことを思い出した。身体の感覚といえば、立っているのもやっとなほど具合が悪い。これは早く誰かに後を任せないと命令系統が突然遮断されて混乱する。そんな当たり前の判断をようやく下せたわたしはユラン伍長を呼んだ。わたしは一体今まで何をしていたのだ!
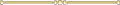
いつもは絹糸のように優しい彼女の髪は埃にまみれて絡まりあっていた。差し込んだ指が絡まり止まる。ちゃんと手入れしていなかったろ、と言いそうになって止めた。言えば確実に張り手が飛んでくる。それも全く悪くはないが、たとえ身じろぎ一つであっても、オスカルの余計な体力の消費が惜しかった。絡まりあった髪束を、手ぐしを通すように解こうとする俺の指をオスカルが押さえた。
オスカルの頬に指を辿らせる。幾すじもの涙が埃と混じって、浅黒い縞模様になっているのだろう、何かざらつくものが指先とオスカルの肌の間にあった。涙の通りあとを横切って、俺が指でなぞる形に涙模様を描いているに違いない。その頬に、僅かでも血の気が残っていることを祈った。次から次へ、新しい涙が俺の指先を濡らし、切れ間のない道筋をオスカルの頬につけていた。
睫毛をそっとなぞると、オスカルはゆっくりと目を細めた。眉根に寄せられた皺。俺はこの表情を何度もさせたのではなかったか。目を怪我した時。群集の襲撃を受けた時。荒れまくっていた時。またやってしまった。オスカルはこんなふうに、俺の傷を自分が受たかのように、いや多分それ以上に痛みをもって受け止める。今まで何故それを思いやれなかったのだろう。そしてわかっていてもなお、こうして同じあやまちを繰り返す俺をどうか許して。
そう思った途端、ふんわりとこんがらがった絹糸が俺の頬に落ちてきた。次に柔らかくて熱をもった唇が右頬に舞い降りた。無言のまま、唇だけが何かを囁くように俺の頬の上でやさしく動き、オスカルの濡れた頬が俺の頬に重ねられる。唇が俺の右の目元まで行き着くと、僅かの隙も残すまいとでもいうように、唇で、頬で俺の肌を埋め尽くしていく。強烈な彼女の想いが俺の身体中を満たした。
『わたしを許して』
俺はしばらくそのままオスカルのくちづけを受けていたが、やがて触れてくる
オスカルの唇と頬の後を追って顔を向けた。互いに触れ合っていた右頬を離さないまま、そこにありったけの気持ちを込めた。
『俺を許して』
オスカルの右口角に触れた唇を、頬骨の方にゆっくりと移動させて許しを乞う。
オスカルは俺の前髪を掻き揚げて、額を経由して左目にくちづけを返してくる。
俺は今度は左を向いて、オスカルの左頬を求める。動く方の右腕でオスカルの肩ごと、後頭部を抱え込む。オスカルはそのまま俺の耳元に唇を寄せる。
『どうか、自分を責めないで』
『お願いだから、おまえを許して』
いつしか、俺たちは交互に自責を手放すことを互いに懇願し合っていた。
俺は、オスカルの頭から下へと手をすべり下ろし、すこしずつ背を探る。
オスカルの胸に巣食う病巣を探すように。できることなら掌から吸い取ってしまいたい。オスカルは俺の意図に気付いたのか、ふっと身体を硬くして俺の肩際、寝台に手をついて、俺と距離を離そうとした。俺はそれを許さない。再びオスカルの後頭部に手をまわす。オスカルの吐息が震え、嗚咽が聞こえた。温かい新たな雫が降ってきて俺の頬を伝い落ち、枕を濡らす。そのままオスカルが落ち着くまで髪をなで、頬を拭う。頬を包み込んで親指でオスカルの唇を静かに往復すると、オスカルは緊張を解いた。
オスカルの頭を軽く引き寄せると、彼女はもう抵抗しなかった。俺の頬が再びオスカルの涙で濡れ、柔らかな唇が羽が落ちるように与えられた。乾いていたオスカルの唇はしっとりと涙で潤い、オスカルそのものが俺の唇に注ぎ込まれる。乾きそうだった魂が息を吹き返す。オスカルから与えられた涙は俺の体の隅々まで染みとおり、失われていた力が湧き起こる。俺はそれを全て唇を通してオスカルに返した。彼女からも柔らかな温もりが、涙の味に染まって戻ってきた。何の言葉も必要なかった。
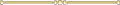
14日の戦闘で負傷した俺とジャンとラサール、そしてアンドレは同じ部屋で世話を受けていたんだ。フランス衛兵はパリで英雄扱いを受けていたから、負傷兵に便宜をはかりたいという申し出がたくさんあったらしい。そのうちの一人がこのお屋敷の持ち主だ。俺は足に一発、ジャンは背中に一発、そしてアンドレは胸から肩に三発喰らった。ラサールは軽症だった。俺もジャンも熱は出たけど気はしっかりしていたけれど、重症だったアンドレはもう3日も意識が戻らない。意識が戻らなければ、栄養も水分も取れないから、銃創の熱で体力が尽きた時が最後だと医者が言っていた。
隊長には絶対そんなことは言うな、ってアランが凄んだけれど、言わなくたって隊長だもの、そんなことわかっていたと思う。そのアンドレがさっき目を覚ました。弱ってはいるけれど、気持ちはちっかりしている。ラサールは隊長に知らせるために飛んで行った。俺たち、隊長を散々困らせたけれど、犯罪まがいのことまでやっちゃったけど、隊長はめげるどころか俺ら以上に強気だった。その隊長が、アンドレが死にかけた時に、今まで見たことのないような憔悴した姿を見せた。だから、アンドレのことも心配だったけれど、俺たちは全員隊長の事を心配していたんだ。
そして、隊長は戻って来た。
「オスカル…!」
アンドレが扉の方を向いて隊長の名を呼ぶ方が先だったような気がする。その後
廊下を走る足音と、サーベルと吊り金具が触れ合う金属音が聞こえたと思ったら、勢い良く扉が開いて隊長が飛び込んで来た。いつもなら、上官であってもきちんとノックをして声をかけてくれる隊長が。泊り込みで親切に世話をしてくれているかわいらしいロザリーさんは、最初驚いたように大きな目を見開いていたけれど、やがて目頭を押さえてそっと部屋を出て行った。
俺もそうするべきなのかな、とは思ったけど、足がギプスでぐるぐる巻きになっているもんだからどうしようもない。がたがたと気の利かない杖音を立てて広い部屋をのろのろと足を引きずって出て行くのも、かえって邪魔くさいよね。なんて、ぐずぐずしているうちに機会を逸してしまった。ロザリーさんのようにすっとスマートにさりげなく出て行ければよかったんだけど。
隊長のあとに従って来たらしいアランと、伝令に行ったラサールが開きっ放しの扉からちょいと顔を覗かせた。隊長はまっすぐにアンドレのベッドに駆け寄って、彼を抱きしめたから、俺たち全員がその後姿をいきなり見ることになった。そして、間の抜けた顔でぼーっと自分のベッドに座っている俺に、『ばーか』ってな目つきを投げて寄越してから、どこかに行ってしまった。
俺は一斑の連中から後でさんざんな目に合うことになるんだけど、その日、俺は一生忘れられない光景を見たのだった。
キスなんて、子供の頃から見慣れていたし、まあ、その男女の営みに繋がるような濃厚で長~いやつではない限り、ただの挨拶みたいなものだと思っていた。
あんな接吻もあるんだ。
兄妹同士とか親友同士のそれではなくて、どう見たってあれは男女の愛情のキスだった。アンドレが隊長を庇って飛び出したところや、その後の隊長の取り乱し方を見れば、2人の間はもうアンドレの一方的な片思いでなどではなくなっていることなんか一目瞭然だった。わからない方がどうかしているよね。だから、まあ、現場を見ちゃったショックやらなんやらの感情は別にして、そのことについては今更驚くようなことではなかったんだ。
でも。
俺が見たのは、キスであってキスではなかった。2人が交わしていたのは、彼ら自身まるごとすべてだったのだと思う。全て。最初は軽く触れ合うだけの接吻だったけど、そのたびに1千の言葉をもってしても形にできない魂の会話が聞えるようだったんだ。勿論俺には隊長とアンドレが、無言で何を話しているかなんてわからない。どうでもいいんだ、そんな事。隊長にはアンドレがいて、アンドレには隊長がいて、それだけでおよそこの世で考えつく望みを遥かに超えて、お互いを満たしている。隊長の病気もアンドレの失明も、その事実の前では何の効力も持っていない。
そう感じた。そう伝わってきた。
美しかった。隊長も含めて、衛兵隊員達はこの三日間、交代で睡眠をとる以外はパリに出ずっぱりだったから、着替えもせずにすっかり汚れきってヒゲもそっていない。隊長にはヒゲはないけれど、似たようなものだったし、アンドレだって意識はなくても、銃創による高熱が続いて汗だくだった。彼の胸をぐるぐるに巻いた包帯は赤黒く血が滲んでいる。
でも、それは俺が今までの人生の中で見たものの中で、一番美しい光景だった。
あんな接吻は初めて見た。接吻と言うよりは、あんな人の繋がり方、と言った方がいいかな。
2人が唇を重ね合った時、俺は感動で涙を流していた。人間にはこれほどまで人を愛する力があるんだ。この先どんなに辛い出来事と出合っても、俺は一生人間を、人間の持つこの最強の力を信じていられる。
アンドレ、アンドレ。
おまえを取り戻した時、私は私も取り戻した。
~To be continued~
気のせいでも、思い込みでもなく、確かに光が見えた。
この薄暗い部屋では、俺の目には人のシルエットすら判別できないはずなのに、オスカルが飛び込んで来た時、ほんの一瞬だったが、眩い光が俺のもとに舞い降りたのを、俺ははっきりと見た。あるいは、それは肉眼で見た映像ではなく、俺の魂がオスカルの魂をとらえたのかも知れない。
言い尽くせないほどの後悔と詫びの言葉。体力の限界を越えた身体への気遣い。隠していた病。戦闘と混沌を生き抜いてくれたことへの感謝。何にもまして変わりようのない愛おしさ。再会の喜び。想いは幾晩語り明かしても伝えきれない。なのに、おまえが俺の名を呼び、俺のもとに走り寄っってその身を俺の枕元に投げ出した時。
俺の首に廻されたおまえの腕に自分の腕を重ね、柔らかな絹糸の束に手を差し入れ、おまえの鼻先を俺の頬に引き寄せた時。暖かい涙で濡れた熱い頬を合わせ、弾む息遣いの愛しさに胸がはち切れそうになった時。
「本当によく…やった…な…」
口に出せたのはたった一言だった。オスカルは、声になるかならないかの小さな吐息で応えた。俺を抱きしめる彼女の力強さ、微かな振るえが充分過ぎるほど想いの全てを語っていた。
交じり合う互いの体温と脈動が、大切なものを取り戻した喜びを静かに謳う。いつしか、ふたりの中を流れる血潮は一つになって二人の体を駆け巡る。それだけで、俺たちは世界を手に入れた者よりも満ち足りていた。
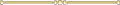
私はどこにいたのだろう。私が私をぼんやりと他人事のように眺めていたような気がする。市庁舎にに通じるサン・トノレ街道は2層の分厚い人垣で延々と埋め尽くされていた。新旧取り混ぜたタイプのマスケット銃が槍のように人垣から突き出ている。果たしてまともな銃弾がこめられているのだろうか。おそらく正規の銃弾など手に入らないだろう。
銃先に銃剣はついていたりいなかったりまちまちだ。槍に鎌、果ては棒切れに荒縄で刃物をくりつけただけの、即席武器も人垣から所狭しと突き出ている。民兵と野次馬の区別もつかないカオスな群衆は『国王万歳!』繰り返し叫んでいる。しかし、その歓声の中には少なからず敵意の混じった『国民万歳!』の怒号も混じっていた。
自分が自分でないような浮遊感の中でも、私は私のすべきことは明瞭に理解していた。思考力も判断力も普通に働いていた。俄か作りの民兵を統括するために、一定の距離で部下を配置する。定期的に状況報告をさせ、非常事態の段階ごとにいく通りかの指示を出す。部下達はよく動いてくれて、熱狂に我を失うことなく、秩序を保つ任務を全うしていた。
国王陛下を乗せた8頭立て馬車が、地味な装飾に鞍替えした軽騎兵に、守られると言うよりは監視されるように取り囲まれて目の前を通り過ぎる。馬車窓を通して口元を真一文字に結んで目を閉じていらっしゃる陛下の横顔がちらと見えた。
それなのに何の感慨も涌かない自分に驚く。その自分をさらに無感動に眺める自分もいる。幾層にも自分自身が分かれて漂っているようだ。地面から巻き上がる埃が目に辛かった。
行列の後からは100名程だろうか、国民議会議員が続き、その後を従僕が大勢続く。鳴り響く太鼓とラッパに大波のような歓声、人いきれ。身体が沸騰するように熱くなったり寒くなったりする。眩暈と頭痛。目を開けているのも辛くなる。せめて喀血だけは起きないで欲しい、とぼんやり思う。身体は辛いのに、それもまるで他人事のように見ている私がいる。
馬車と行列は遠ざかって行った。国王陛下がパリ市庁舎に到着したのちに何が起きるのだろう。群集は一向にその場を離れようとはしなかった。街中が機能を止めて事態を見守っている。
「隊長!」
誰かが叫んだ。ぐらり、と身体が傾いて急に地面が近くなった。地面にたたきつけられる、と思う間もなく太い腕がわたしを抱き留め、わたしの視界を遮った。気づけばその腕に体重をあずけたわたしの一部が悲鳴を上げた。違う!この腕ではない!何が違うのかもわからないまま、心のどこかが悲鳴をあげ続けている。遠い遠い声。
負傷して休んでいるはずの部下が知らせを届けてくれたのはその時だった。彼の意識が戻った!
幾重にもぶれていたわたしが一人になった。感覚が蘇った。目に映る情景が急に色彩を取り戻し、この世には色というものがあったことを思い出した。身体の感覚といえば、立っているのもやっとなほど具合が悪い。これは早く誰かに後を任せないと命令系統が突然遮断されて混乱する。そんな当たり前の判断をようやく下せたわたしはユラン伍長を呼んだ。わたしは一体今まで何をしていたのだ!
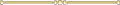
いつもは絹糸のように優しい彼女の髪は埃にまみれて絡まりあっていた。差し込んだ指が絡まり止まる。ちゃんと手入れしていなかったろ、と言いそうになって止めた。言えば確実に張り手が飛んでくる。それも全く悪くはないが、たとえ身じろぎ一つであっても、オスカルの余計な体力の消費が惜しかった。絡まりあった髪束を、手ぐしを通すように解こうとする俺の指をオスカルが押さえた。
オスカルの頬に指を辿らせる。幾すじもの涙が埃と混じって、浅黒い縞模様になっているのだろう、何かざらつくものが指先とオスカルの肌の間にあった。涙の通りあとを横切って、俺が指でなぞる形に涙模様を描いているに違いない。その頬に、僅かでも血の気が残っていることを祈った。次から次へ、新しい涙が俺の指先を濡らし、切れ間のない道筋をオスカルの頬につけていた。
睫毛をそっとなぞると、オスカルはゆっくりと目を細めた。眉根に寄せられた皺。俺はこの表情を何度もさせたのではなかったか。目を怪我した時。群集の襲撃を受けた時。荒れまくっていた時。またやってしまった。オスカルはこんなふうに、俺の傷を自分が受たかのように、いや多分それ以上に痛みをもって受け止める。今まで何故それを思いやれなかったのだろう。そしてわかっていてもなお、こうして同じあやまちを繰り返す俺をどうか許して。
そう思った途端、ふんわりとこんがらがった絹糸が俺の頬に落ちてきた。次に柔らかくて熱をもった唇が右頬に舞い降りた。無言のまま、唇だけが何かを囁くように俺の頬の上でやさしく動き、オスカルの濡れた頬が俺の頬に重ねられる。唇が俺の右の目元まで行き着くと、僅かの隙も残すまいとでもいうように、唇で、頬で俺の肌を埋め尽くしていく。強烈な彼女の想いが俺の身体中を満たした。
『わたしを許して』
俺はしばらくそのままオスカルのくちづけを受けていたが、やがて触れてくる
オスカルの唇と頬の後を追って顔を向けた。互いに触れ合っていた右頬を離さないまま、そこにありったけの気持ちを込めた。
『俺を許して』
オスカルの右口角に触れた唇を、頬骨の方にゆっくりと移動させて許しを乞う。
オスカルは俺の前髪を掻き揚げて、額を経由して左目にくちづけを返してくる。
俺は今度は左を向いて、オスカルの左頬を求める。動く方の右腕でオスカルの肩ごと、後頭部を抱え込む。オスカルはそのまま俺の耳元に唇を寄せる。
『どうか、自分を責めないで』
『お願いだから、おまえを許して』
いつしか、俺たちは交互に自責を手放すことを互いに懇願し合っていた。
俺は、オスカルの頭から下へと手をすべり下ろし、すこしずつ背を探る。
オスカルの胸に巣食う病巣を探すように。できることなら掌から吸い取ってしまいたい。オスカルは俺の意図に気付いたのか、ふっと身体を硬くして俺の肩際、寝台に手をついて、俺と距離を離そうとした。俺はそれを許さない。再びオスカルの後頭部に手をまわす。オスカルの吐息が震え、嗚咽が聞こえた。温かい新たな雫が降ってきて俺の頬を伝い落ち、枕を濡らす。そのままオスカルが落ち着くまで髪をなで、頬を拭う。頬を包み込んで親指でオスカルの唇を静かに往復すると、オスカルは緊張を解いた。
オスカルの頭を軽く引き寄せると、彼女はもう抵抗しなかった。俺の頬が再びオスカルの涙で濡れ、柔らかな唇が羽が落ちるように与えられた。乾いていたオスカルの唇はしっとりと涙で潤い、オスカルそのものが俺の唇に注ぎ込まれる。乾きそうだった魂が息を吹き返す。オスカルから与えられた涙は俺の体の隅々まで染みとおり、失われていた力が湧き起こる。俺はそれを全て唇を通してオスカルに返した。彼女からも柔らかな温もりが、涙の味に染まって戻ってきた。何の言葉も必要なかった。
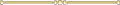
14日の戦闘で負傷した俺とジャンとラサール、そしてアンドレは同じ部屋で世話を受けていたんだ。フランス衛兵はパリで英雄扱いを受けていたから、負傷兵に便宜をはかりたいという申し出がたくさんあったらしい。そのうちの一人がこのお屋敷の持ち主だ。俺は足に一発、ジャンは背中に一発、そしてアンドレは胸から肩に三発喰らった。ラサールは軽症だった。俺もジャンも熱は出たけど気はしっかりしていたけれど、重症だったアンドレはもう3日も意識が戻らない。意識が戻らなければ、栄養も水分も取れないから、銃創の熱で体力が尽きた時が最後だと医者が言っていた。
隊長には絶対そんなことは言うな、ってアランが凄んだけれど、言わなくたって隊長だもの、そんなことわかっていたと思う。そのアンドレがさっき目を覚ました。弱ってはいるけれど、気持ちはちっかりしている。ラサールは隊長に知らせるために飛んで行った。俺たち、隊長を散々困らせたけれど、犯罪まがいのことまでやっちゃったけど、隊長はめげるどころか俺ら以上に強気だった。その隊長が、アンドレが死にかけた時に、今まで見たことのないような憔悴した姿を見せた。だから、アンドレのことも心配だったけれど、俺たちは全員隊長の事を心配していたんだ。
そして、隊長は戻って来た。
「オスカル…!」
アンドレが扉の方を向いて隊長の名を呼ぶ方が先だったような気がする。その後
廊下を走る足音と、サーベルと吊り金具が触れ合う金属音が聞こえたと思ったら、勢い良く扉が開いて隊長が飛び込んで来た。いつもなら、上官であってもきちんとノックをして声をかけてくれる隊長が。泊り込みで親切に世話をしてくれているかわいらしいロザリーさんは、最初驚いたように大きな目を見開いていたけれど、やがて目頭を押さえてそっと部屋を出て行った。
俺もそうするべきなのかな、とは思ったけど、足がギプスでぐるぐる巻きになっているもんだからどうしようもない。がたがたと気の利かない杖音を立てて広い部屋をのろのろと足を引きずって出て行くのも、かえって邪魔くさいよね。なんて、ぐずぐずしているうちに機会を逸してしまった。ロザリーさんのようにすっとスマートにさりげなく出て行ければよかったんだけど。
隊長のあとに従って来たらしいアランと、伝令に行ったラサールが開きっ放しの扉からちょいと顔を覗かせた。隊長はまっすぐにアンドレのベッドに駆け寄って、彼を抱きしめたから、俺たち全員がその後姿をいきなり見ることになった。そして、間の抜けた顔でぼーっと自分のベッドに座っている俺に、『ばーか』ってな目つきを投げて寄越してから、どこかに行ってしまった。
俺は一斑の連中から後でさんざんな目に合うことになるんだけど、その日、俺は一生忘れられない光景を見たのだった。
キスなんて、子供の頃から見慣れていたし、まあ、その男女の営みに繋がるような濃厚で長~いやつではない限り、ただの挨拶みたいなものだと思っていた。
あんな接吻もあるんだ。
兄妹同士とか親友同士のそれではなくて、どう見たってあれは男女の愛情のキスだった。アンドレが隊長を庇って飛び出したところや、その後の隊長の取り乱し方を見れば、2人の間はもうアンドレの一方的な片思いでなどではなくなっていることなんか一目瞭然だった。わからない方がどうかしているよね。だから、まあ、現場を見ちゃったショックやらなんやらの感情は別にして、そのことについては今更驚くようなことではなかったんだ。
でも。
俺が見たのは、キスであってキスではなかった。2人が交わしていたのは、彼ら自身まるごとすべてだったのだと思う。全て。最初は軽く触れ合うだけの接吻だったけど、そのたびに1千の言葉をもってしても形にできない魂の会話が聞えるようだったんだ。勿論俺には隊長とアンドレが、無言で何を話しているかなんてわからない。どうでもいいんだ、そんな事。隊長にはアンドレがいて、アンドレには隊長がいて、それだけでおよそこの世で考えつく望みを遥かに超えて、お互いを満たしている。隊長の病気もアンドレの失明も、その事実の前では何の効力も持っていない。
そう感じた。そう伝わってきた。
美しかった。隊長も含めて、衛兵隊員達はこの三日間、交代で睡眠をとる以外はパリに出ずっぱりだったから、着替えもせずにすっかり汚れきってヒゲもそっていない。隊長にはヒゲはないけれど、似たようなものだったし、アンドレだって意識はなくても、銃創による高熱が続いて汗だくだった。彼の胸をぐるぐるに巻いた包帯は赤黒く血が滲んでいる。
でも、それは俺が今までの人生の中で見たものの中で、一番美しい光景だった。
あんな接吻は初めて見た。接吻と言うよりは、あんな人の繋がり方、と言った方がいいかな。
2人が唇を重ね合った時、俺は感動で涙を流していた。人間にはこれほどまで人を愛する力があるんだ。この先どんなに辛い出来事と出合っても、俺は一生人間を、人間の持つこの最強の力を信じていられる。
アンドレ、アンドレ。
おまえを取り戻した時、私は私も取り戻した。
~To be continued~
新着コメント
- もんぶらん ⇒ Sweet but Bitter Days ★New★だけど再掲 ☆
- まここ ⇒ Sweet but Bitter Days ★New★だけど再掲 ☆
- もんぶらん ⇒ ヴァレンタイン2018 Bitter Sweet
- もんぶらん ⇒ 影たちの挑戦 ★New★
- まここ ⇒ ヴァレンタイン2018 Bitter Sweet
- リヴァイラブラーフル ⇒ 影たちの挑戦 ★New★
- もんぶらん ⇒ ヴァレンタイン2018 Bitter Sweet
- まここ ⇒ ヴァレンタイン2018 Bitter Sweet
- もんぶらん ⇒ 影たちの挑戦 ★New★
- もんぶらん ⇒ 影たちの挑戦 ★New★
